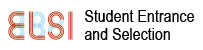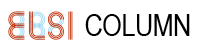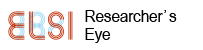過去の見学レポート
SSH指定校の高校生がELSIを見学
2014年8月7日、新潟県立新潟南高等学校から2年生の生徒9名と教員1名が地球生命研究所にお越しになりました。
午前中は玄田英典准教授が「太陽系の惑星と系外惑星」と題し、太陽系の惑星の特徴から、系外惑星の生命の存在の可能性の話まで、約90分の講義を行いました。生徒たちからは地球外生命の探査法などハビタブルゾーン(生命居住可能領域)についてなどの質問があがりました。
 玄田准教授の講義を聞く高校生ら
玄田准教授の講義を聞く高校生ら学食で昼食をとったあとは、木村淳研究員の講義「氷下の未知なる海:地球外生命圏への期待」でした。木村研究員は太陽系の中での生命の可能性について話し、特に、内部に海があるといわれている木星の衛星エウロパの研究や探査計画について説明しました。生徒たちからは実際にどうやって探査機から衛星の内部を調べるのか、衛星に直接穴を掘らずに調査する方法などについての質問がありました。
 木村淳研究員の講義を聞く高校生ら
木村淳研究員の講義を聞く高校生ら
講義後はELSI棟内を見学し、コミュニケーションスペースや和室など、イメージと違う研究所の姿に驚きの声があがっていました。
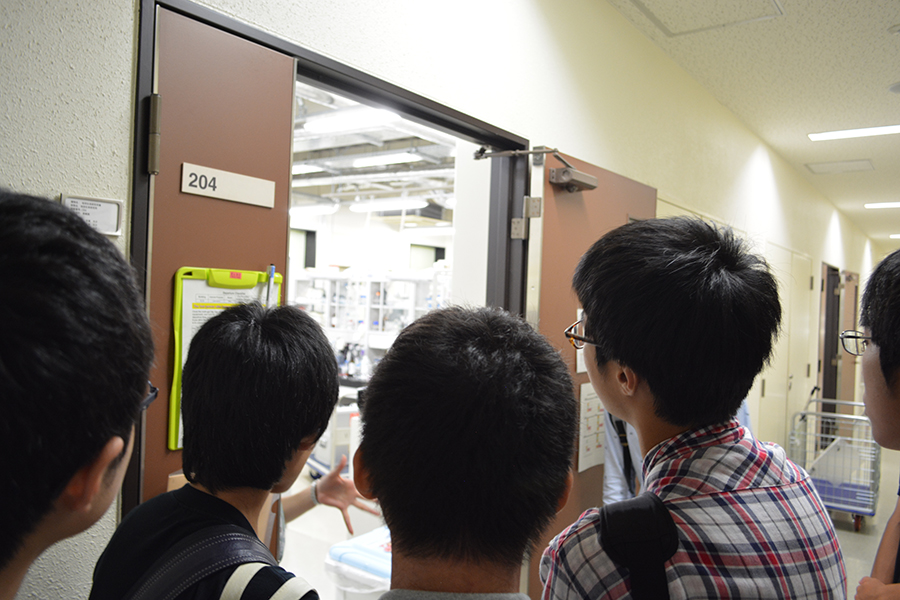 実験室を興味深く見つめていました
実験室を興味深く見つめていました====講師紹介====
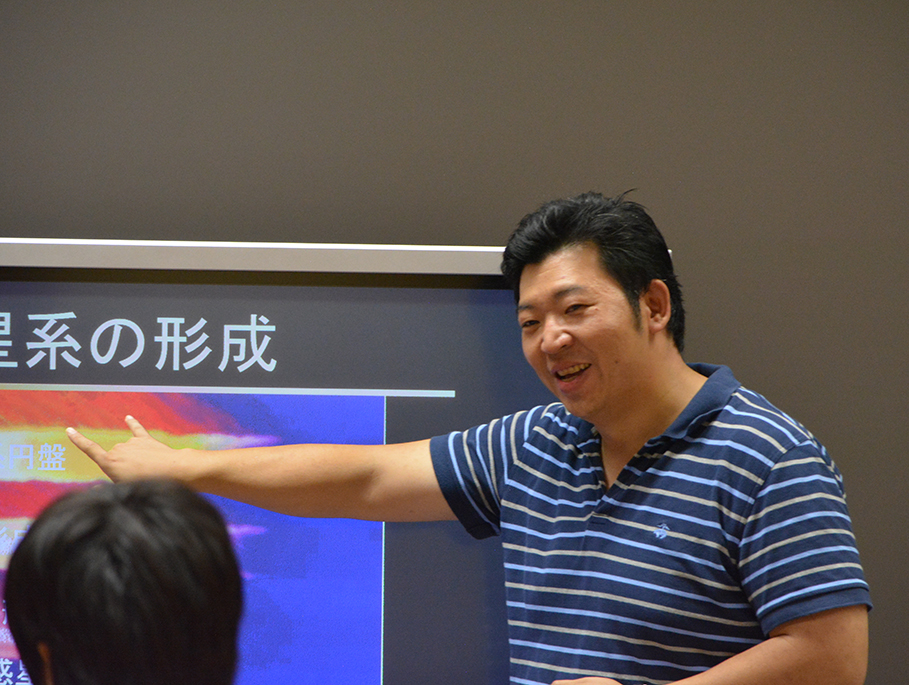 玄田准教授
玄田准教授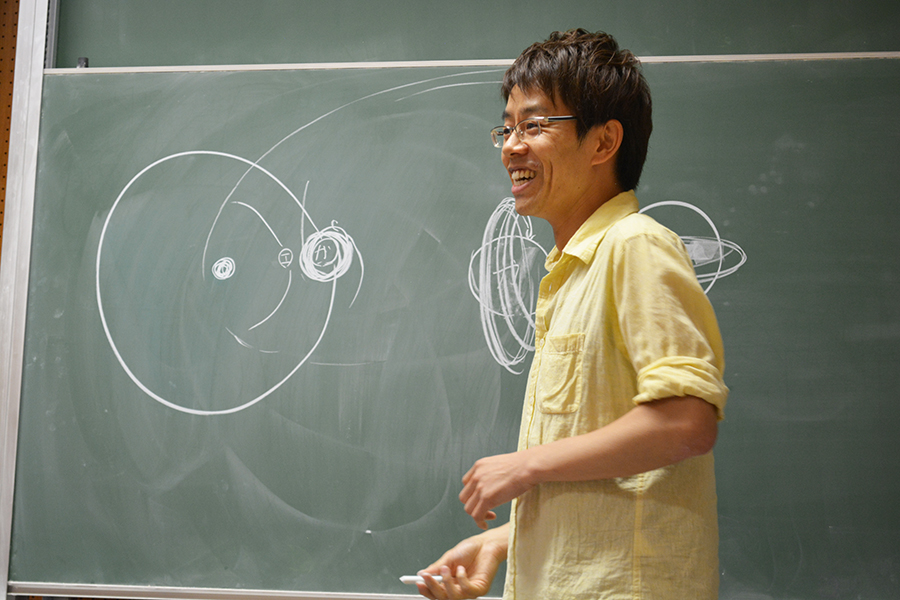 木村淳研究員
木村淳研究員専門分野:惑星地質, 内部進化, 惑星探査
研究概要:太陽系の巨大惑星領域には表面を氷に覆われたいわゆる「氷衛星」が普遍的に存在し,多様な地質や内部構造を持っています。氷衛星が見せるこうした多様性は,太陽系全体の天体の多様な進化を解き明かす上で格好のサンプルであるという意識のもとで,氷衛星の地質構造の形成や内部進化について,数値シミュレーションや画像解析を主なツールとして研究しています。 また,一部の氷衛星では内部に液体水の海を持つ可能性が示唆されており,氷衛星は固有の生命圏を持っているかもしれません。地球における生命誕生の状況と氷衛星の海環境とを対比させることによって,生命科学に対する新たな視座が与えられる可能性もあります。生命が発生する形態は地球環境が唯一なのか?氷衛星にも,特有の生命を生む条件が存在するのではないか?という問いにも迫れると考えています。 また地球の月についても,日本の月周回衛星SELENE/かぐやの取得したデータなどを用いて地質や内部進化の研究を行っており,氷衛星との比較を通して,固体天体がどのような過程を経て現在目にするような特徴を持つに至ったのかに興味を持っています。 惑星探査ミッションとしては,2007年度より「かぐや」プロジェクトに参加し,観測機器運用計画の立案,データアーカイブシステムの設計・開発などを担当してきました。さらに現在は次期月探査SELENE-2プリプロジェクトでのミッション検討チームや,はやぶさ2プロジェクトでのレーザ高度計(LIDAR)チーム,また国際協同計画であるJUICE(JUpiter ICy moons Explorer:木星氷衛星探査機)ミッションでのレーザ高度計(GALA: GAnymede Laser Altimeter)チームに所属し,科学検討を進めています。